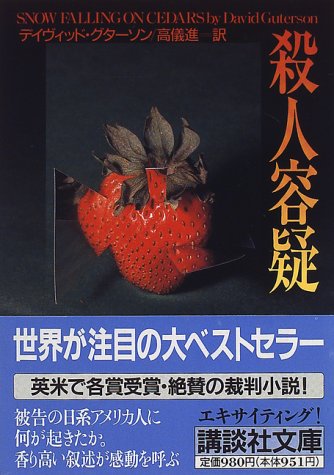ヒューストン市警殺人課刑事スチュアート・ヘイドンを主人公とする第5弾で1992年発表作。本作をもってシリーズは途絶えている。
振り返れば、捜査活動をメインとするオーソドックスな警察小説は、第1作「噛みついた女」のみで、以降一作ごとに物語の軸を大きく変えている。ただ、現代社会の不条理な暴力の有り様を探究し、その闇にジャーナリスティックな視点で切り込む骨太な姿勢は不変。重厚な語り口は更に深みを増し、リンジーが到達した文学的境地を物語る。とにかく、これまでの作品をも凌駕する熱量/テンションには圧倒された。ミステリという範疇では収まらない多様な読み方が出来るシリーズの集大成に相応しい傑作。
富豪マラー家の娘リーナが、中米グアテマラで失踪した。平和活動家として同国貧困層の支援に携わっており、フリー・ジャーナリストの男と行動を共にしていた。或る事件でマラー家と知り合っていたヘイドンは、リーナ発見と保護に力を貸して欲しいと頼まれた。言い知れぬ暗い予感を覚えながらもヘイドンは承諾。警察を休職し、グアテマラへと飛ぶ。
1960年から続いた激しい内戦で多くの血が流れた国。軍事クーデター後は独裁体制が敷かれ、今も政情不安が続いていた。腐敗の極みにあり、インディオ/マヤ民族に対する差別と虐殺が横行。ゲリラとの戦闘も絶えず、治安は悪化の一途を辿っていた。独裁政権は麻薬カルテルと結託、暴力装置同然の軍隊と警察は反政府グループを容赦なく弾圧した。
マラー家は先に私立探偵フォスラーにリーナ捜索を依頼していた。ヘイドンとは旧知の仲だった。だが、現地に探偵の姿はなく、滞在していたホテルの部屋は争った形跡があり血塗れだった。リンジーはリーナの友人ジャネット・ピットナーを訪ねる。米国大使館に勤めるジャネットの夫は、何かを隠すような不審な態度を見せた。ヘイドンは、リーナの僅かな痕跡を追うが一向に行方を掴めない。そんな中、元CIA工作員ケイジが接触してきた。かつては敏腕の国外要員だったが、離脱後は情報屋として現政府の闇に通じているらしい。
後日の夜、再び姿を現したケイジは、ヘイドンを或る場所へと連れて行く。モルグだった。そこには見るも無惨な女の死体。願い虚しく間に合わなかったのか。なぜ彼女は殺されたのか。真相を追い求めるヘイドンが出口の見えない迷宮でもがくほどに事態は不可解さを増していった。
序盤から漂う凄まじい暴力の匂い。それは主人公が動く先々で死人が出るという展開で可視化される。敵か味方か判然としないケイジに翻弄されつつ、否応もなく主人公は〝狂気の果て〟へと引き摺り込まれていく。
間もなくヘイドンは、消えた女に関わる虚偽と事実を見極め、腐敗した国家の最底辺でうごめく非人道的犯罪を知る。物語の根底にあるのは、道理無き暴力に晒され続けてきた者たちの怒りと哀しみであり、狂った社会の中で生きざるを得ない焦燥と無常だ。腐り切った権力者と、それに付き従い私利私欲を貪る俗物の群れ。弱い者は常に虐げられ、やがては破滅する。その巨悪と対峙し、無残な事実を白日の下に晒し、どう駆逐するか。
リンジーは、人間の根源的な悪の本質に迫る地獄巡りを主人公に課す。ヘイドンの物語が本作をもって絶えた理由は、スケールが大きくなりすぎて、一介の刑事に負わせる役回りを遥かに超えてしまったからではないか。本シリーズは、事件に没入し沈思黙考するヘイドンと、過剰に深入りして心身を病む夫を思いやる妻の繊細で温かいやりとりも魅力のひとつだったが、本作ではささやかな幕間は省かれ、一人の男がグアテマラで視る狂気の様相を語ることに焦点を絞っている。下手なホラー小説を超える恐怖を覚える流れもあり、逃げ場のないまま読み手は終始緊張感を強いられる訳だが、ページを捲る手を止めることはできないだろう。
情景は暗く濁り、闇はどこまでも深い。強烈で生々しいリアリズム、繊細な描写によって生まれるリリシズム。終盤に向かうほど高まっていくダイナミズム。時に冷徹に、時に劇的にシーンを印象付けるリンジーの卓越した筆力に唸る。
辿り着いた〝狂気の果て〟で何が待ち受けるのか。終幕の余韻は余りにも重い。
評価 ★★★★★