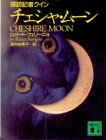英国の出版社ハーパー・コリンズ社がアガサ・クリスティーの作品を対象に「差別的表現」を削除した改訂版を出すと報じていた。「現代の読者にとって不快と思われる表現」について出版社独自の判断で修正を加える訳だが、当然物故している作者の〝意志〟は不問となる。クリスティーを選んだ理由は、恐らく国民的作家であり、その作品が世界中で読まれているからだろう。勘ぐれば、英国を代表するミステリ作家が「差別的表現」を使うことは許されない、という意図があるのかもしれない。同社以外でも、既にロアルド・ダールの児童書などにも変更が加えられているという。
当たり前だが、ミステリに限らず文学/芸術は、その作品が生まれた時代、社会的状況、そして作者自身の思想を反映するものだ。読者は人種や性、階級や障害者らに対する差別的表現に触れることで、その時代に何が〝問題〟であったかを識る。
そもそも〝由緒正しき名探偵〟は差別的発言をしない/してはならない、という定義がおかしい。ミステリの主人公が聖人君子である必要性など無く、まして「本格ミステリ」に登場するようなアクが強く高慢ともいえる探偵らが、平然と人種差別の言動をするさまに読者が違和感を覚えることなど殆どないだろう。たとえエルキュール・ポアロが論理的ではない先入観のみで「ユダヤ人」を侮辱する発言をしたとしても、当時の英国における偏見/差別、その社会的認知が登場人物/語り手に投影されているだけであり、それはクリスティーと大半の読者が共有していた価値観/通念であったに違いない。これは何処の国でも同じであり、日本の文学など差別的表現で溢れかえっている。小説では、主要な人物(もしくは書き手)の偏った思考や行動はストーリー展開にも大きく影響することもあるため、安易に削除すればプロットの根幹をも破壊しかねない。
だが、出版社の余計な配慮によって、それらは「無かった」ことになる。あたかも差別無き平等な社会であったと誤解させることは、極端に述べれば歴史の改竄に近く、作品そのものの価値をも歪める。「差別的表現」を削除する対象が、優生思想に基づくあらゆる差別遂行を主張したアドルフ・ヒトラーの「我が闘争」ではなく、クリスティーの大衆的ミステリだから「許される範疇」なのではない。今現在も万人に読まれ続けている娯楽小説であるからこそ、根深く浸透していた差別意識/状況をそのままに伝えるべきではないだろうか。さらに文献をあたり、歴史を紐解けば、差別された側の闘いの軌跡も学ぶこともできる。つまり、同社の改訂を大袈裟に述べれば、作品を通して差別問題を考え、その撤廃に向けての行動を促す機会を読者から奪うことにも通じる。
事実を認識せずして、どう差別と向き合い、差別無き社会実現へと歩むことができるだろうか。
実は先般、日本でも相似する出来事があった。広島市教育委員会が小中高で使う平和教育の教材から、原爆投下後のヒロシマを描いた名作「はだしのゲン」を削除するというものだ。具体例として「子どもが浪曲を歌って小銭を稼ぐシーンについて『浪曲は現代の児童の生活実態に合わない』、母親に食べさせようと池の鯉を盗むシーンについては『鯉盗みは誤解を与えるおそれがある」』などの理由を挙げている。被爆した少年が愛する家族の飢えをしのぐために為した〝盗み〟を断罪し「教育」上の観点から抹消しようとした。ここにも手前勝手な正義の意識、裏を返せば偽善が露呈している。そもそも、なぜ「広島/長崎に原爆を落とされたのか」を検証することもなく、天皇制ファシズムによって軍国主義をひた走り、無謀な侵略戦争によって自国他国を問わず殺し続けた国家の責任を問うこともなく、焦土と化した地で懸命に生きようともがいた人々の姿を「現代の生活実態に合わない」などと都合の良い解釈を加えた上で「いつの時代でも日本人は清く正しくあった」と子どもたちに、それこそ「誤解を与える」ことを教育だと主張しているのである。その一方で現代の子どもたちは戦争ゲームなどの仮想現実の世界で、武器を手に取り暴力まみれの遊びに浸っている。これを見て見ぬ振りをしたまま、平和を考えるためにはこれ以上のない教材となる「はだしのゲン」を消し去ろうとする矛盾。
歴史の事実/暗部に墨を塗り、犯罪や差別が無かったことにしようとするのは、中途半端で歪んだ理想主義に過ぎず、現代の子どもらに何の教訓も授けることはない。
ミステリに話を戻せば、欧米のスパイ/冒険小説に於いて戦中や戦後しばらくは日本やドイツなどは敵/悪の象徴となり、当たり前のように差別的表現をされる。これは、戦時下の日本が米英やアジア諸国に偏見を持ち唾棄したことと同様で、時の権力者らがイデオロギーを用いて植え付けたレイシズムの表れだ。その事実を作品の中で描いているからといって、読み手は作者が偏向しているとは、通常であれば捉えない(右翼/保守であれば別だが)。
時代にそぐわない表現だから修正する。子どもたちに悪影響を与えかねないから削除する。ならば犯罪を扱うミステリ小説そのものが否定されることになる。けれども、描かれた殺人や窃盗などに刺激を受けた読者が犯罪者に変貌することは、まずあり得ない。ミステリには、基本的に推理する楽しさを求めるのであって、作品中に「差別的表現」を認めるか否か、不快に感じるか否かは、読み手の読解力と経験次第だ。そこに問題を感じたならば、時代背景や作者自身について徹底的に調べ、考察し、その後の言動に変化をもたらすだろう。
時にミステリには人間社会の闇が生々しいまでに刻印されていることがある。その闇から目を逸らして(逸らさせて)、何の意味があるというのか。